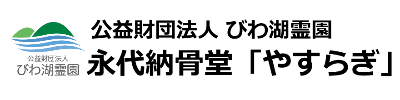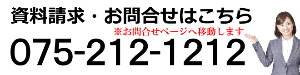ここは、滋賀・京都エリアで改葬(お墓の引っ越し)や永代供養・納骨を考えている方向けに、信頼できる公的情報(一次情報)だけを1ページにまとめた案内ページです。
難しい専門用語をできるだけ避け、初めての方でも迷わないように、手順→根拠→公式リンクの順で並べています。まずは全体像をつかみ、必要な部分だけ公式ページをご確認ください。
本ページのポイントは3つです。
① 改葬や納骨の流れを一目で理解できる
② 迷ったらすぐに公式サイト(行政・法令・公的機関)へ飛べる
③ ご事情に合わせて当サイト内の案内(費用・見学・Q&A)にも戻れる
この3点です。
このページの使い方(3ステップ)
STEP1:まず「重要リンク10選」をざっと眺める
すぐ見るべき公的リンク10選に、法令・自治体・公的機関の入口を集約しました。ここを上から順に軽く確認しておくと、全体の道筋がつかみやすくなります。
STEP2:自分に関係する部分だけ深掘りする
手続きの流れ(超やさしく)で大まかな順番を把握し、該当する自治体ページ(滋賀・京都の公営斎場と自治体ページ)で具体的な窓口や必要書類を確認します。季節の法要日が気になる方は、季節の供養カレンダーをご覧ください。
STEP3:迷ったらQ&Aとご相談へ
よくある質問とトラブルを避けるポイントをチェックしてから、詳細は当サイトのお問い合わせページにお進みください(※URLはサイトの実際の構成に合わせて差し替えてください)。
まずはここから:すぐ見るべき「公的リンク10選」
信頼できる一次情報に限定しています。青文字をクリックすると各公式サイトが新しいタブで開きます。
- 厚生労働省|墓地・埋葬等のページ(法律・通知の総合案内)
- e-Gov法令検索|墓地、埋葬等に関する法律(法律本文)
- e-Gov法令検索|墓地、埋葬等に関する法律施行規則(具体的な規則)
- 大津市|改葬許可申請について
- 大津市|斎場(火葬場)案内
- 京都市|京都市中央斎場
- 国立天文台|二十四節気・雑節(令和7年/2025年)
- 国民生活センター|墓・葬儀サービス(相談件数・傾向)
- 長浜市|改葬許可の申請手続き
- 守山市|改葬許可の申請について
※公式サイトは内容が更新されることがあります。ブックマーク推奨/毎月1回のリンク確認をおすすめします。
手続きの流れ(超やさしく・図解イメージで)
改葬なしで永代供養を探す場合(今あるお墓から遺骨を動かさない/これから火葬する遺骨を納骨する)
手続きの考え方
今あるお墓から遺骨を移動しない場合は「改葬許可」は不要です。これから火葬するご遺骨を永代供養に納める場合は、火葬後に発行される「埋葬許可証(火葬許可証の埋葬欄)」を納骨時に提出します。
流れ(超やさしく)
① 希望条件を整理する
立地(通いやすさ)/費用(総額・年会費の有無)/供養スタイル(個別安置・合祀・納骨堂・樹木葬)/お参りのしやすさ(駐車場・時間帯)をメモします。
② 永代供養先を候補出し → 資料請求・見学予約
候補を3件ほど選び、資料を取り寄せて見学予約。パンフレットだけで判断せず、現地で雰囲気・導線・管理体制を確認します。
③ 見学当日の確認ポイント
費用の内訳(含む・含まない)/年間の供養(彼岸・合同法要の有無)/使用期間や更新の要否/納骨時に必要な書類(埋葬許可証)/返金・キャンセル規定をチェックします。
④ 申し込み(契約)
申込書を記入し、支払い方法と納骨日の仮決め。必要に応じて僧侶手配や法要内容(読経の有無・塔婆など)を相談します。
⑤ 納骨の準備
これから火葬する場合は、火葬手続き→火葬→「埋葬許可証」を受領し、納骨当日に原本を持参。手元供養から納骨する場合は、施設の指示に従い、骨壺サイズや持ち物(位牌・遺影など)を確認します。
⑥ 納骨当日
受付→必要書類の提出(埋葬許可証など)→読経・納骨→控え書類の受け取り。
⑦ 事後の手続きと記録保管
申込控え・領収書・埋葬許可証のコピー・法要案内などは1つのファイルに保管。年中行事の予定もカレンダーに控えます。
注意ポイント
費用は「基本料金に何が含まれるか」を必ず確認(骨壺サイズ制限、銘板刻字、法要の有無、永代管理料、更新料)。「個別安置」か「最初から合祀」かで将来の取り扱いが変わるため、写真や現物で保管形態を確認。案内の更新や休場日は公式ページで最終確認を。
法律・手続きの参考(一次情報の見方)
これから火葬する場合は、市区町村で火葬許可→火葬→埋葬許可証(納骨時に提出)の流れです。条例や要綱は各自治体の公式ページで確認してください。
改葬ありで永代供養を探す場合(今あるお墓・納骨堂から別の永代供養先へ遺骨を移す)
手続きの考え方
遺骨を別の場所へ移す行為は「改葬」にあたり、今ご遺骨がある市区町村で「改葬許可」の申請が必要です。交付された許可証(原本)は新しい納骨先に提出します。
流れ(超やさしく)
① 新しい納骨先を決める(受入証明書をもらう)
候補:永代供養墓/納骨堂/樹木葬/一般墓。現地見学で費用内訳・供養方法・安置形態を確認し、申込前に「受入証明書(受け入れますという証明)」の発行可否と発行手順を確認します(改葬許可申請で必須)。
② 現在の墓地・納骨堂で証明書をもらう
管理者に「埋蔵(収蔵)証明」の作成・押印を依頼。墓地使用者と申請者が異なる場合は承諾書等が必要なことがあります。必要書類・印鑑・身分証などを事前確認します。
③ 市役所で「改葬許可申請」
提出書類の例:改葬許可申請書/受入証明書/埋蔵(収蔵)証明書/本人確認書類/手数料など。書式・手数料・窓口は自治体ごとに異なるため、必ず公式案内を確認。郵送や委任での申請が可能な場合もあるので、遠方の方は可否を問い合わせます。
【補足】申請書の記入イメージ
自治体公式ページのPDF見本や記入例を参照。記入欄(申請者・埋葬者・改葬先・理由)を間違えないよう、見本どおりに丁寧に記入します。
④ 改葬許可証の受領 → 新しい納骨先へ提出 → 納骨
交付された「改葬許可証(原本)」を新しい納骨先に提出。当日忘れがないようクリアファイルで管理。納骨日に合わせ、僧侶の手配や法要準備、親族への連絡を進めます。
⑤ 原墓所の撤去・原状回復(必要な場合)
石碑撤去や整地が必要なら、現地見積もり→日程調整→作業立会いの可否を確認。管理者への完了報告や書類の受領が必要なことがあります。
⑥ 事後の手続きと記録保管
申請書控え・改葬許可証のコピー・受入証明書・領収書・作業報告書などを1つのファイルにまとめ、将来確認できるようにしておきます。
注意ポイント
順番が大切:「受入証明」→「埋蔵(収蔵)証明」→「改葬許可申請」→「許可証交付」→「納骨」。
順番を崩すとやり直しになりやすい。
費用の内訳(基本料金・合祀/個別・銘板・法要費・永代管理料・撤去費)と含まれないもの(お布施、搬送費など)を必ず確認。
スケジュールは余裕を持ち(お彼岸・お盆は混雑)、書類取り寄せ・押印・窓口対応に時間がかかる前提で逆算します。
法律の根拠(一次情報の見方)
改葬は「墓地、埋葬等に関する法律」および施行規則に基づく手続きです。申請窓口・様式・手数料・必要書類は各自治体の公式案内を最終根拠とします。疑問点は一次情報(法令本文・自治体告知)を確認し、不明な場合は担当課へ電話で照会するのが確実です。
滋賀・京都の公営斎場と自治体ページ
大津市の火葬場案内
利用時間・予約・休場日・持ち込み可否・料金などは公式ページで最新情報をご確認ください。年ごとに更新される事項(休場日PDF等)があるため、手続き直前に再確認すると安全です。
京都市中央斎場
受付時間、休場日、申請方法、必要書類などは京都市公式ページをご確認ください。繁忙期(お彼岸・お盆前後)は早めの確認・予約をおすすめします。
その他、滋賀県内の改葬・墓地案内
季節の供養カレンダー(お彼岸の日付の根拠)
春・秋のお彼岸は、天文学的な二十四節気(春分・秋分)がもとになっています。年ごとの正確な日付・時刻は国立天文台の暦要項で確認できます。法要日や法要準備のスケジュールを決める際の根拠としてご活用ください。
トラブルを避けるための注意ポイント
公的機関の相談事例から見える「つまずきやすい点」を3項目にしぼってお伝えします。どれも基本を押さえれば回避できます。
① 料金の内訳と範囲を明確に
想定外の費用や、セットに含まれる内容の誤解が相談の火種になりがちです。見積書では、何が含まれていて何が含まれていないか(例:戒名料・お布施・法要会場費・骨壺・搬送費)を確認し、不明点は事前に質問しましょう。
② 書類と手順の「順番ミス」をしない
改葬は受入証明 → 埋蔵(収蔵)証明 → 改葬許可申請 → 許可証 → 納骨の順番が重要です。とくに許可証の原本は納骨日に必ず持参し、当日忘れを防ぐためクリアファイルにひとまとめにして管理してください。
③ 公式ページで必ず「最新情報」を確認
休場日・手数料・窓口の変更などは年度や時期で変わることがあります。SNSやまとめサイトではなく、一次情報(自治体・法令・公的機関)を最終判断の根拠にしてください。
よくある質問(やさしいQ&A)
Q1:分骨のときも、市役所で「改葬許可」が必要ですか?
A:分骨は状況によって扱いが異なります。まずは現在の墓地管理者に相談し、分骨証明書など必要書類の有無を確認しましょう。自治体の「改葬Q&A」に解説がある場合もあるので、大津市の改葬案内のような公式ページも参考にすると安心です。
Q2:どのくらい前から準備すれば良いですか?
A:書類の準備・押印・窓口の混雑などで想定より時間がかかることがあります。お彼岸・お盆など繁忙期の1〜2か月前から動き始めると安心です。僧侶の手配や親族の日程調整も早めに進めましょう。
Q3:法律や規則はどこで確認できますか?
A:墓地、埋葬等に関する法律(本文)と、施行規則が一次情報です。条文が難しいときは、厚生労働省の解説ページの概要が役立ちます。
Q4:火葬場の予約や休場日はどこで確認しますか?
A:各自治体の公式ページを確認してください。例:大津市の斎場案内/京都市中央斎場
Q5:遠方に住んでいても手続きはできますか?
A:書類の郵送対応や委任状での手続きが可能な場合もあります。「現在お骨がある市区町村」の窓口(改葬担当)に、郵送・委任の可否と手順を事前確認しましょう。
自然に「権威サイトへ発リンク」する文章例(コピペOK)
例文1:手続きの冒頭で公式案内に誘導する
改葬の申請は現在お骨がある市区町村で行います。必要書類や窓口、手数料は自治体の公式ページで最新をご確認ください。大津市の方はこちら(改葬許可申請)をご覧ください。
例文2:根拠(一次情報)にまっすぐ案内する
手続きの根拠は、墓地、埋葬等に関する法律と、施行規則に定められています。概要は厚生労働省の解説ページが分かりやすいです。
例文3:季節行事の日時に客観的根拠を添える
春・秋のお彼岸は、天文学上の春分・秋分が目安です。正確な日付は国立天文台の暦要項(2025年)でご確認ください。
例文4:注意喚起を中立的に示す
費用やサービス内容で迷ったら、国民生活センターの相談動向も参考になります。契約書・見積書は内訳と含まれる範囲を必ず確認しましょう。
当サイト内の関連ページ
公的リンク(再掲・ブックマーク用)
- 厚生労働省|墓地・埋葬等のページ
- e-Gov|墓地、埋葬等に関する法律
- e-Gov|墓地、埋葬等に関する法律施行規則
- 大津市|改葬許可申請
- 大津市|斎場(火葬場)
- 京都市中央斎場
- 国立天文台|二十四節気(2025)
- 国民生活センター|墓・葬儀の相談動向
- 長浜市|改葬許可の申請手続き
- 守山市|改葬許可の申請について
無料相談・見学のご案内
永代納骨堂「やすらぎ」にお申込みいただけることは、大変有り難くまた嬉しいことです。
しがし、私達のいちばん大切な役割は、あなた様がお墓のことで困っていること・悩んでいること、その問題解決のお手伝いをすることです。
ですから、「やすらぎ」のご提案の前に、あなた様のお墓のことでの、困りごと・悩み・問題を理解し、共感し、一緒に解決の道を考えていくことが重要だと考えております。
最終的に、当永代納骨堂があなた様のお役に立てないこともあるかもしれません。
しかし、あなた様の困りごと・悩み・問題の良き理解者・共感者となり、良き相談相手になることは可能です。
永代供養・納骨・墓じまい(改葬)のことで、「こんな悩みはどうすればいい?」「自分の場合はどう動けばいい?」という個別の無料相談や、実際の永代納骨堂「やすらぎ」の資料請求・見学は、お問い合わせページから承っています。合祀しない個別安置で、季節の法要や日々のお参りがしやすい環境をご用意しております。ご事情・ご希望を伺いながら、最適な解決策や進め方をご提案します。どうぞ安心してご相談ください。